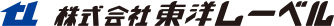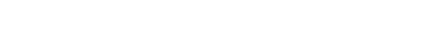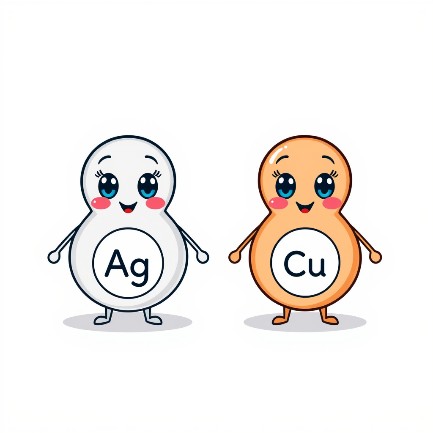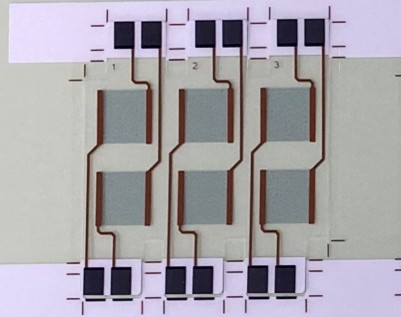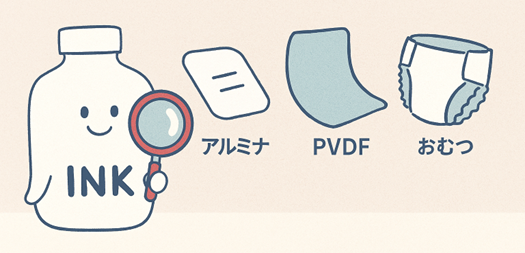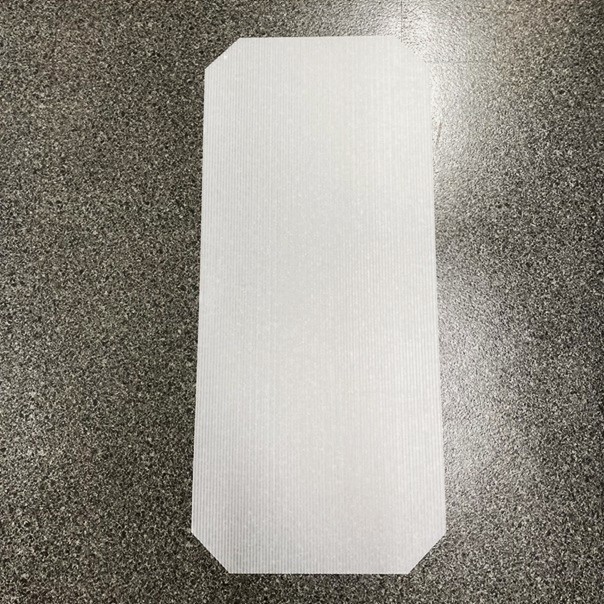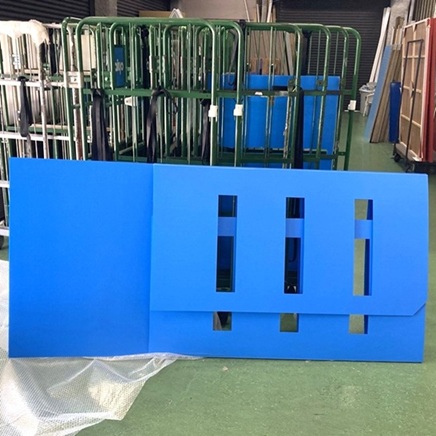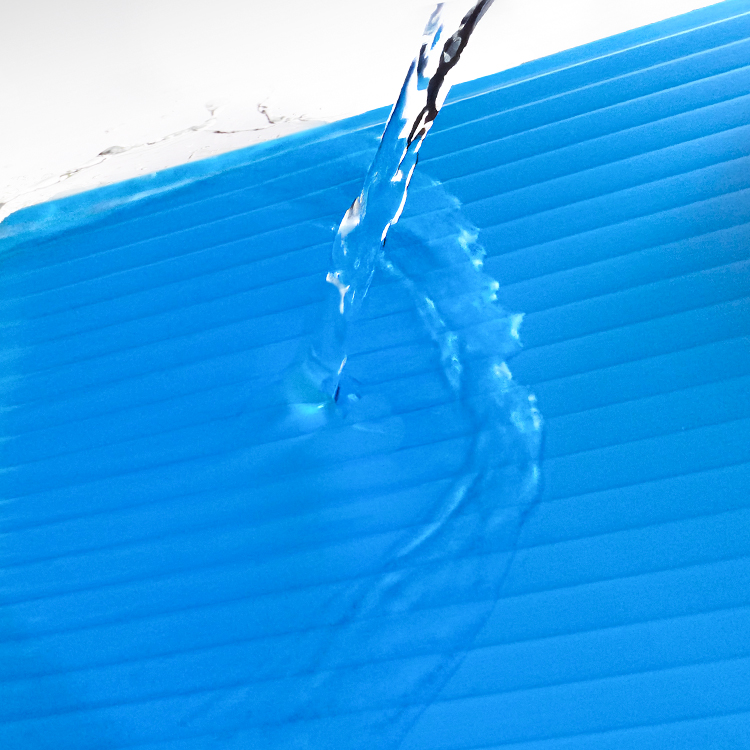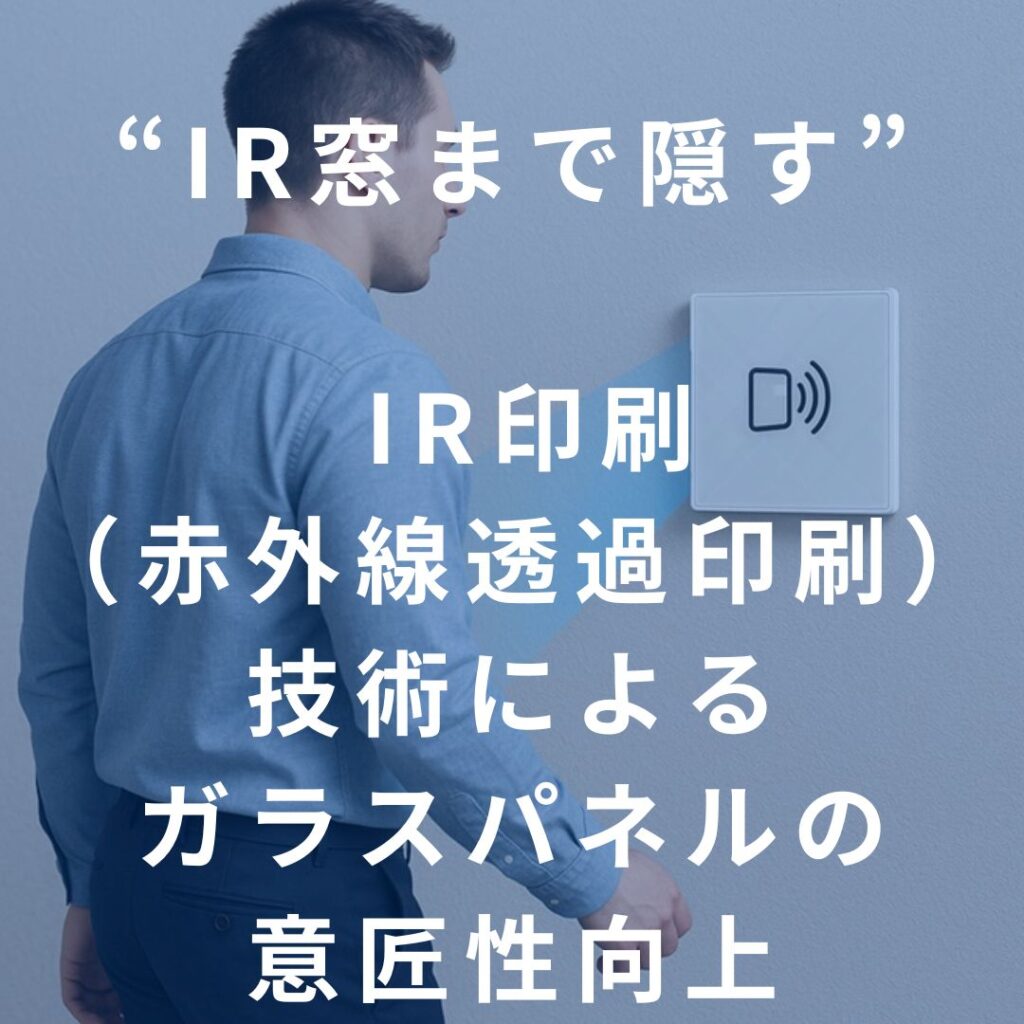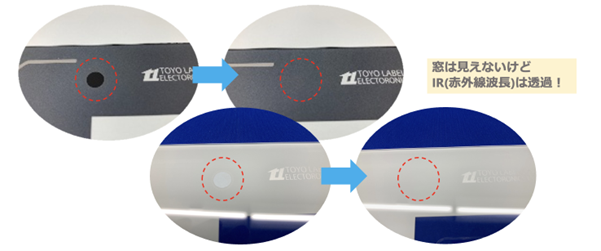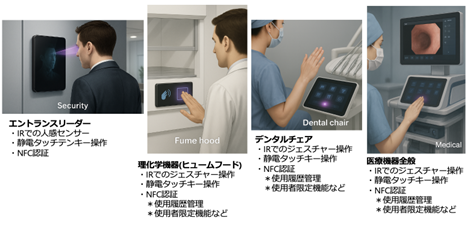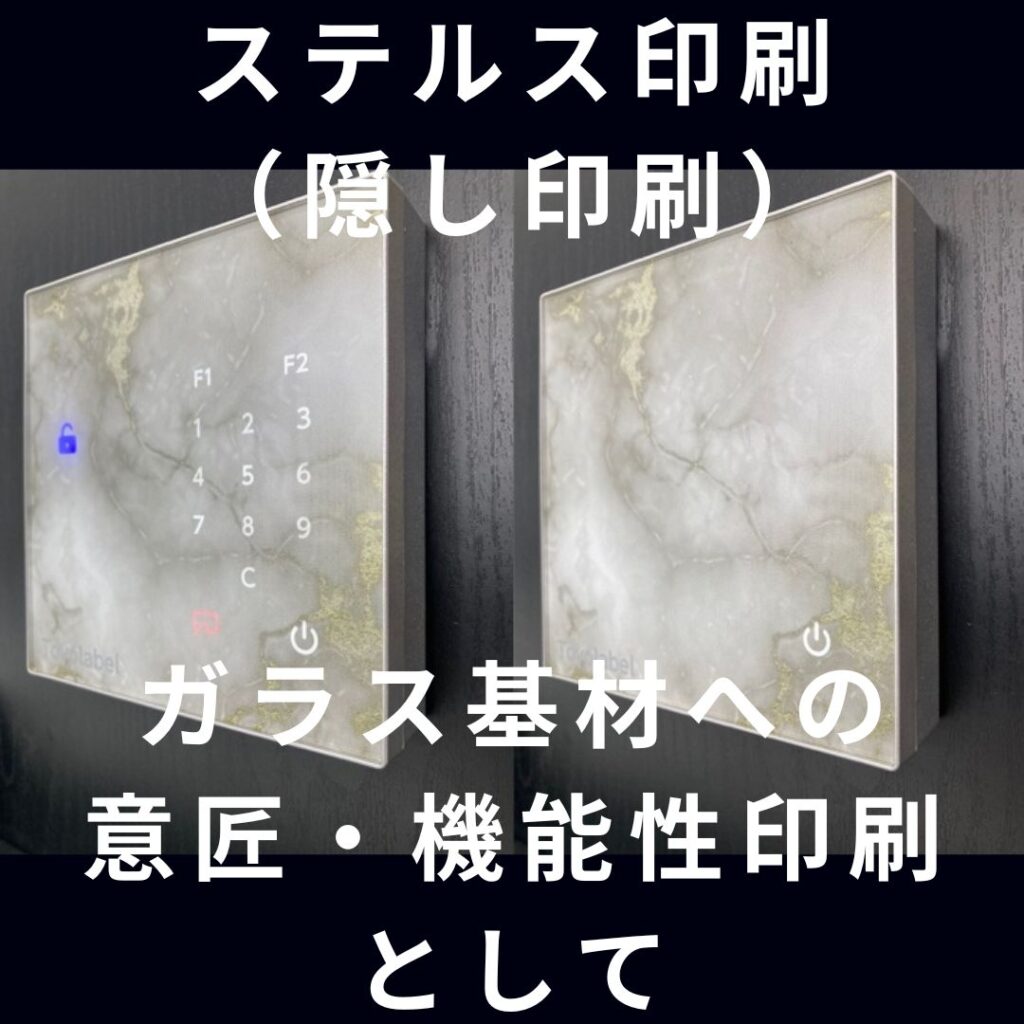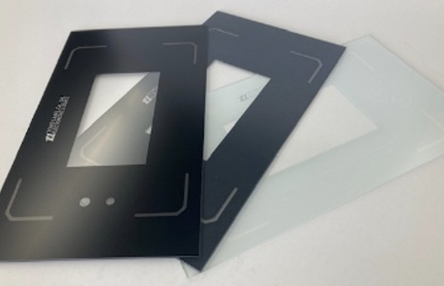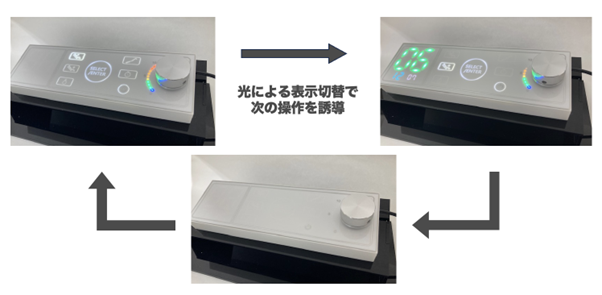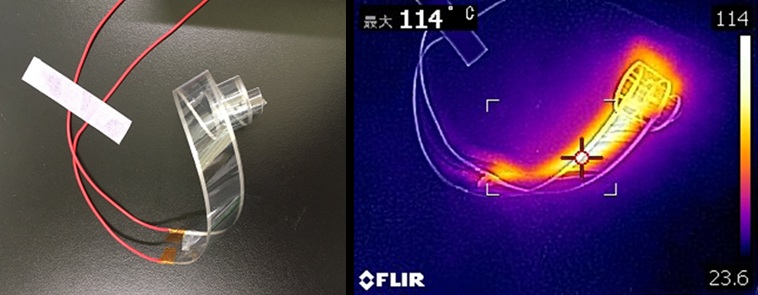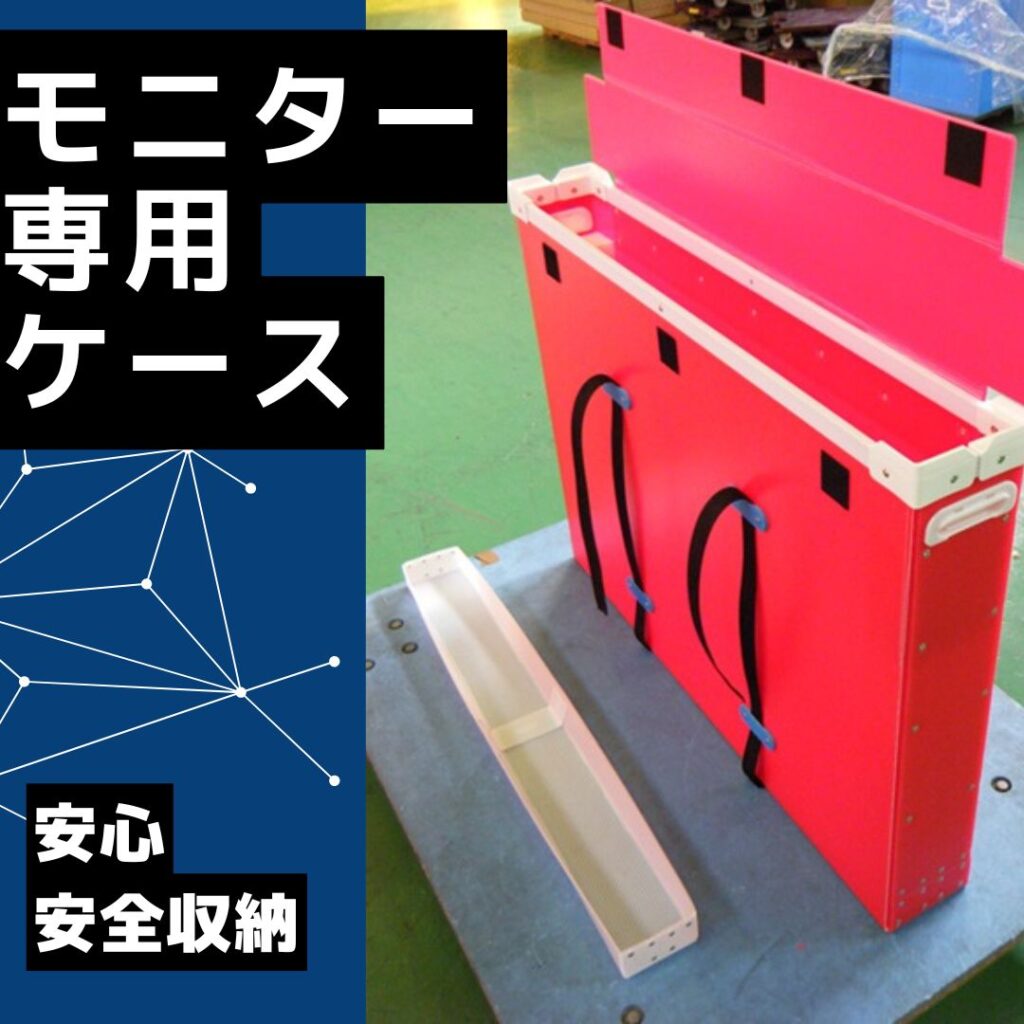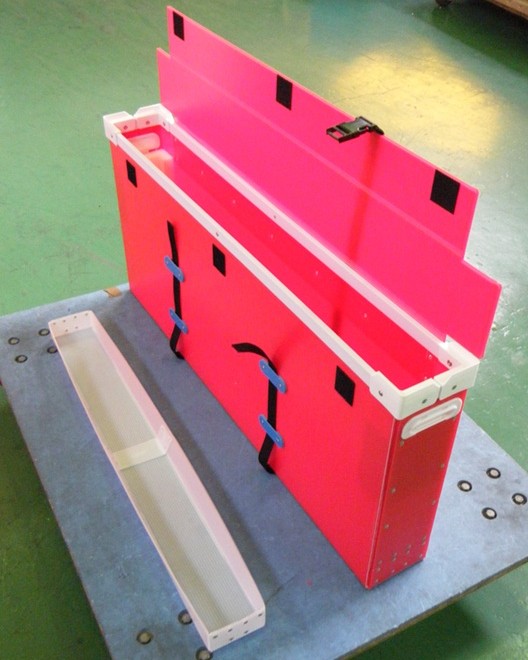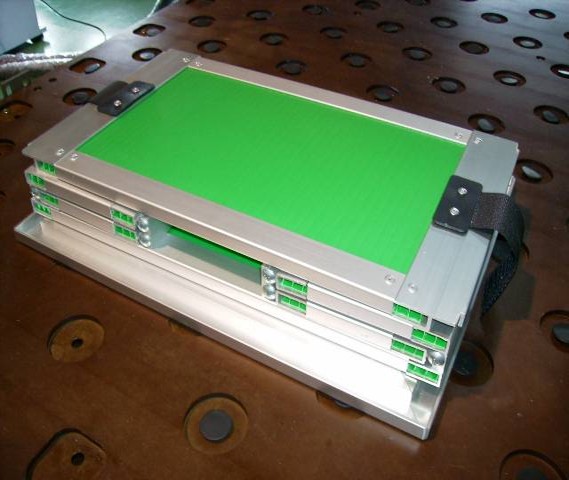技術がつながると、未来が動き出す
—
みなさま、明けましておめでとうございます。
新しい一年が、みなさまにとって明るく、心おどる一年になりますように。
そして本年も東洋レーベルをどうぞよろしくお願いいたします。
午年らしく、今年も元気に駆け出していきたいところです。
まずは、年明け一発目のコラムということで、
今回はちょっとワクワクする“技術の組み合わせ話”をお届けします。
—
東洋レーベルの展示会にお越しの方はご存じかと思いますが、
当社はセンサーやヒーターだけではなく、液体・湿度検知の技術も持っています!
また、フィルムだけではなく、布や不織布にも印刷をすることができるので、
組み合わせ次第でいろんなセンサーを作ることが可能です!!
—
例えば、
▼センサー×ヒーター×液体・湿度検知
雨や結露を感じて、自動で開閉する仕組みができます。
天文台の屋根や住宅の天窓にいかがでしょう。
▼センサー×ヒーター
この組み合わせだけでも、人や動物がいる場所だけを温めるヒーターや、
融雪や結露・凍結防止にも活躍できそうです。
▼ヒーター×液体・湿度検知
水漏れや浸水を検知し、そのまま乾燥まで。
「気づく」と「対処する」を1枚で完結することが可能です。
カメラでは見えない、検知できない部分をセンサーで補うことができます。
また、東洋レーベルでは布や不織布にも印刷することが可能なので、
質感はもちろん、防水性や撥水性、伸縮性などの様々な機能を付与し、
デザインにもこだわったセンサーを製造することが可能です!
—
東洋レーベルの技術を組み合わせたセンサーは、
すでに多くのお客様からお問い合わせをいただいており、
詳細はまだお伝えできませんが、今年いよいよ量産がスタートする予定です!
さらに当社では、基板設計から制御、センサー、筐体、意匠面にいたるまで
すべてを社内にて一気通貫で製造できる体制を整えています!
だからこそ、アイデア段階のご相談から量産まで、スムーズに進めることが可能です!!
—
今年も午年らしく、勢いよく駆け出していきます。
東洋レーベルの技術も、みなさまのアイデアとともに、
さらに大きく“走り”を広げていきますので、どうぞご期待ください!!
(このコラムは、開発部R.T. が担当しました。)
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。